80年代の画面表示技術
ファミコンも SEGA SG-1000 も MSX も、今年(2013年)の夏で30周年。
また、「テレビの父」と呼ばれる高柳健次郎氏の命日も7月23日だったそうです。
高柳氏は、日本で最初にブラウン管に表示を行った人(実用レベルとしては世界初)。最初の被写体は、「イ」の文字でした。1990年没。
以前から、当時の画面技術に関して記事を書きたいと思っていたので、良いタイミングだと考えて書かせてもらいます。(これを書き始めたのは7月23日。公開は27日。案外時間がかかってしまった…)
あまりハード寄りの話にはせず、「あんな感じの絵を描いてみたい」という人が読める程度にとどめます。なんとなく、要望が多いようなので。
ただ、自分が技術話が好きなので、適当に技術寄りの話題を挟みます。
絵師さんのための情報は最後にまとめますので、技術部分がわからなければ読み飛ばしながら進んでも大丈夫です。
(最後になって、技術話が必要だと感じた場合は、戻って読めばいいだけです)
目次
MSXの画面について(別ページ)
ファミコンの画面について(別ページ)
50年代の画面表示技術(別ページ)
走査線
当時のアナログテレビは、ブラウン管を使用し、走査線によって画面を作っていました。
当時のゲーム機は、この「走査線」を前提に作られているため、この仕組みから理解しないといけません。
もう絶滅しそうな技術なので詳細に書いておきます。ファミコンをリアルタイムで遊んだ世代には当たり前の話とは思いますので、知っている場合は読み飛ばしてください。
ブラウン管とは「陰極線管」の一種、広い意味では真空管です。
ガラス管の中を真空にし、電極を通したものは広い意味で「真空管」ですが、それでは白熱電球も真空管になってしまいます。
白熱電球自体に説明が必要な世の中がすぐに来そうなので説明しておきましょう。
白熱電球は、抵抗の高いフィラメントに電気を通し、熱を持つことで光らせる仕組みになっています。熱を持ったフィラメントはすぐに「焼き切れる」ため、ガラス管の中を真空にして燃えない(酸化しない)ようにしてあります。
この時、フィラメントは熱によって高いエネルギーを持った「熱電子」が存在しています。熱電子はエネルギーが高いため、簡単に電線を飛び出そうとします。
電線の近くに鉄板を置き、プラスの電荷にします。すると、マイナスの電荷をもっている熱電子はフィラメントから飛び出し、プラスの電極に飛び込むことで電流が生じます。
熱電子は陰極側にしかないので、電流の向きを制限する整流効果を持つことになります。このような、電気的に特別な意味を持った場合に、本来の意味での「真空管」と呼ばれるようになります。
真空管では、フィラメントを陰極(Cathode)、電子を受ける板を陽極(Plate)と呼びます。
ここで、陽極の中央に大きな穴を開けておくと、電子は受け止められず、遠くに飛び出して行きます。この仕組みを「電子銃」と呼び、飛び出した電子は陰極線(Cathode ray)と呼ばれます。
Grid の先に Plate を置けば、単に整流するだけでなく、Grid の電圧によって Plate に流れる電流を制御できる。
このような効果は、増幅作用・スイッチング作用と呼ばれる。
ENIAC では、このスイッチング作用を利用して計算を行った。
パソコンのモニタを CRT と呼ぶことがありますが、陰極線管(Cathode Ray Tube)の略です。今ではブラウン管は使われませんが、過去の名残で今でもそう呼ぶことがあるのです。
また、CRT はもっと単純に「Tube」とも呼ばれます。YouTube は「あなたのテレビ」という意味を持っています。
さて、話をブラウン管に戻しましょう。
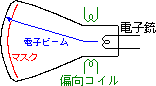 真空にしたガラス管の中に、電子ビームを発射できる「電子銃」がつけてあります。
真空にしたガラス管の中に、電子ビームを発射できる「電子銃」がつけてあります。
電子ビームはマイナス電子の流れですから、電磁石(コイル)によって曲げることができ、照射位置を変えられます。
ブラウン管の表面には蛍光物質が塗ってあり、電子ビームが当たると光ります。これによって画面に色を出します。
 写真は、国立科学博物館に展示されていた、高柳氏がテレビ開発黎明期に使用したブラウン管。
写真は、国立科学博物館に展示されていた、高柳氏がテレビ開発黎明期に使用したブラウン管。左端が電子銃で、中央あたりに「枠」のようについているのがコイル。コイルの部分で曲がるため、ここから先はガラス管が広がり、右端には「蛍光物質」が塗られているので透明ではなくなっている。
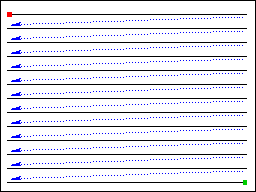 電磁石は、横方向と縦方向につけられていて、左から右へ高速に、上から下にゆっくりとビームを誘導します。
電磁石は、横方向と縦方向につけられていて、左から右へ高速に、上から下にゆっくりとビームを誘導します。
右図でいうと、左上の赤い点から始まり、右方向に画面を1ライン表示します。
右端まで行くと青点矢印のようにビームの照射位置は「次のライン左端」まで戻ります。(この間はビームを出していないので見えません)
右下の緑色の点まで進むと、再び左上の赤い点に照射位置を戻します。この時、少し時間がかかりますが、この時間のことを「垂直帰線期間」と呼びます。ゲームを作るうえでは大事な概念です。
パソコンゲームなどで、画面上のキャラの数によって進行速度が安定しないものがあったのは、パソコンでは垂直帰線期間を検出できない場合があったため。
 さて、左から右に描かれるビームの直線を「走査線」と言います。
さて、左から右に描かれるビームの直線を「走査線」と言います。
写真は、国立科学博物館に展示されている、高柳氏が行った実験の再現の写真。(記事執筆時点では、1日3回、各1時間の動作展示です)
ファミコンの時代…アナログカラー放送時には、走査線は250本程度集まって画面を覆い尽くしていました。
「程度」と表現しているのは、アナログテレビは画面の端が隠れて見えないのが普通だったためです。
(厳密に言えば525本あった)
この走査線を作るビームを強弱させれば、画面上の光も強弱します。
うまくタイミングがあっていれば、意味のある図形が現れます。
ビームを赤・青・緑の3本用意すれば、カラー画面も作れます。
赤のビームは赤の蛍光体にしか当たらないように、マスクと呼ばれる穴だらけの板を用意しておきます。